これまでの経歴や都度考えてきたこと、感じてきたことなどをまとめています。6,000字ほどの長文になりますので、ご関心のある方は読み進めていただければ幸いです。
プロローグ
近所にあまり年の近い子どもがいなかったこともあり、物心ついた頃には、いつもひとりで遊んでいた子どもでした。
内向性が強く、吉本新喜劇の影響を色濃く受けた大阪の中学生のノリについて行けなかったことから、中学生時代は信頼できる友人もおらずそこそこ孤立。
妄想の中、読書にふける思春期を過ごすことになります。
「自分の人生、このままではいけない」と一念発起し、高校に入りアメリカンフットボール部に入部。歴史のある名門チームで痛みと苦しみの鍛錬の日々を過ごします。
毎日、泥人形のようになりながらも、ちっぽけな自分の限界を日々超えることにより、自らの心身が鍛えられていく歓びを経験しました。
チームは大阪府で優勝するも、自分は骨折・入院により長期欠場。
一時は中心選手だったものの、いつのまにかポジションが無くなっているという悲哀も経験しましたが、良い友にも恵まれ、総じて楽しい思い出にあふれる自己改革の日々でした。
その後、大学に進学。同期の主力達は関西学院大学や立命館大学、京都大学など関西のフットボール強豪校に進学する中、私の母校は下部リーグ所属。
どうしようかなと思っていたところ「高校経験者」としての入学情報が出回っており(笑)、引き続き、アメリカンフットボールに取り組むこととなります。
大学4年時にはキャプテンを拝命し、闘う集団のなかで荒くれた男達をまとめるリーダーの役割を全うすることにも向き合いました。
黎明(夜明け前)
大学生活も後半、いよいよ自分のキャリアもしっかり決めていかなければならない時です。
子どもの頃に読んだ『三国志』の中で活躍する武将や賢人たちの物語に心躍らせていた私は、フットボールを通じて自己改革により心身ともに研ぎ澄まされていたこともあり、「社会の役に立ちたい」と大きな志を抱くようになります。
結果、公の仕事で世の中に奉仕するというキャリアを描きました。
どうせやるなら「てっぺん」を目指そうと、当時、自分の大学からはほとんど合格者の出ていなかった国家公務員Ⅰ種試験に挑むこととなり、恩師のすすめもあってさらに2年間の大学院生活を送ることとなります。
さすがにその学費までは親に負担してもらうわけにもいかず、学費負担のため夜はスポーツクラブのトレーナーとしてはたらき、また、お世話になった母校アメリカンフットボール部のコーチをしたりと、「受験生」「大学院生」を含めた四足のわらじを履きながら試験勉強に取り組むこととなります。
東大生や京大生に比べ、地頭のあまり良くないことを自覚する私は「量で勝つしかない」と狂ったように勉強しました。
朝方、夜明け前の空を見ながらたばこを吹かし「自分の人生、どうなるんやろう」と長い夜を過ごしたこともありました。
同時に「夜明け前が一番暗い」という、誰かの諺を目にし、心が熱くなったのも覚えています。
このときの経験から「芽が出るかどうかわからない」というチャレンジに向き合う人の苦しみには、結構共感できる自分がいますし、それは本当に尊いことだと心から思います。
霞ヶ関へ
とはいえ、猛勉強の甲斐あってか、地方公立大学から当時はまだ狭き門だった国家公務員Ⅰ種試験に合格。官庁訪問や面接を経て霞ヶ関の官僚に採用され、周りの人達からも多くの祝福をいただきました。
農業関係の団体職員であった父が一番喜んでくれていたように思います。
こうして、私の人生は光の当たる道を歩くはずでした。
希望を持って上京し向かった霞ヶ関では働きぶりも評価もされ、会社で言うと「経営企画」みたいな部署、大臣のお膝元で働く栄誉にも恵まれました。
これにより、日本を動かす官邸の現場やダイナミックな政権交代も間近で経験することとなります。これらは「キャリア」といわれる官僚の中でもほんの一部分の人間にしか体験できない場所でありましょう。
ただ、同時に、役所の中で目にしたのは、熱い想いを持った優秀な人達の魂が削られ、疲弊していく現場でもありました。
「政治主導」の名のもとに翻弄され、皮肉と諦めに満ちた空気の中、周囲では身体を壊したり、家族が離散したり、時に命を失ったりする人もちらほら。
いつしか自分にも「永久労働機関」というあだ名がつき、機械のように仕事に埋没。深夜の帰宅、2〜3時間寝て出勤するという日々を繰り返していました。
人間が持つ力は大きく、苦難にも耐え抜く力を備えてはいますが、人の心は意味の感じられない仕事には耐えられません。
世界的な不況への対応や不祥事も重なり限界を迎えた自分の心身はフリーズし、出勤しようとしても家から一歩も足が出ないという事態を迎えます。
自分の心とつながらず、頭だけを使って働く限界を学ぶ良い時間となりました。
ここではじめて自分の人生と真剣に向き合うことになります。
あなたは何をしたいのですか?
自分は何がしたいのか、自分の使命とは何か、はたしてこのままの道を進んで良いのだろうか…。
専門家の助けを借りてひたすら内省しました。このときの経験がコーチとしての自分の原点となります。
苦しい心中を吐露する自分の話に共感し、真摯に話を聞いてくれたコーチが最後に放ったひとことはおおいに自分を覚醒させるものでした。
「本当に大変な状況で、いろいろと愚痴やいいわけはつきないと思います。」
「苦しい思いはいっぱい伝わってきます。」
「ただ、あなたの言葉からは「何がしたいのか」が全く聞こえてこないのです。」
「あなたは一体何をしたいのですか?」
この質問にわたしは沈黙し、眠れない夜を一晩過ごしました。そして、翌朝、コーチに対して長いメールを打つことになります。
心から伝えたかったのは、人間の強さと弱さ。
脱藩
その夜、頭に思い浮かんていたのは、泥にまみれていたあの頃の記憶でした。
キャプテンとして部員達に声をかけ続けていたあの日。もっと頑張ればもっと強くなるのに、なぜ、みんなそこそこしか頑張らないのだろう。
どうやったら人は本気になるのだろうか。何が人を突き動かすのだろうか。
また、思い返されるのは行政の現場で感じていた違和感でもありました。
制度や補助金で保護すればするほど、思考停止し、力を失っていく現場。
本来優秀なはずの人々が、なぜ、これほどまでに思考停止するのだろう。
なぜ、これほどまでに熱さを失うのだろう。
衰退産業であった農業においても、活気のある現場には必ず熱い「人」がいます。周りの常識に負けず、熱い思いを持って周囲をインスパイアし続ける「若者」「ばかもの」「よそもの」たち。
こういう人がいる地域は元気です。
予算や制度により、世の中の仕組みをつくる仕事をし続けてきた私は、人の心が動くことの重要性に目がいくようになりました。
やはり「仕組み」を超えて現実を動かすのは人間の「スピリット」であると。
コーチングのパートナーとともに数年かけて内省した後、海外大使館勤務への打診を機に「ここがタイミング」と決意を定め約12年間勤めた霞ヶ関を退職。
コーチとしてひとり起業する決断をしました。
「脱藩官僚」として、大海原へひとり舟をこぎ出した瞬間です。
出航、即沈没寸前
しかしながら、このコーチという業界「コーチングをする人」よりも「コーチにビジネスを教える人」の方が多い業界でもあります。
ある友人は、魚類の中で最も多くの卵を産卵し成魚になる率が著しく低いといわれる「マンボウ」を例としてこの様子を表現していましたが、的を射たたとえだと思います。
コーチングの業界は参入障壁が低いが故に「多産多死」の世界。私みたいに会社を飛び出した「稚魚」達の多くは、自ら顧客を広げることができず、様々なビジネス系のプレイヤーの餌になっていくという現実があります。
ご多分に漏れず、私自身も貯金残高は急降下。
2ヶ月後には銀行残高がゼロになるという危機まで追い込まれました。
「コネなし、客なし、ビジネス経験無し」「かつ官僚出身でプライドだけは高い」という、ビジネスマンとしては300%ぐらいどうしようもなかった私は、完全に世の中をなめきっていたのだと思います。
そんなマインドで生き残れるわけが無い。
ただ、自分にとって一つ幸運だったのは「哲学」という最上位の知に出会えたことでした。
売上をあげるための西洋哲学
哲学といっても、哲学の先生に哲学を学んだわけではありません。
私にとっての幸運は、師がケタ違いの売上げを上げてきた「セールスマン」だったことです。
彼は、現代のすべての学問の源流である哲学が教えてくれる「高い視点から物事を捉える力」を駆使して独自の方法論を編み上げ、高額の商材を扱うセミナーセールスで常時成約率50%以上という驚異の実績をたたき出していました。
そして、継続的に年間二億円以上のビジネス教材を売り歩き、某セミナー会社の発展に大きく貢献した、業界では伝説のセールスマンでした。
私は、彼がまとめ上げた方法論を駆使して一気に売上げをあげ大復活を果たします。
同時に、ビジネスマンとしてのマインドもたたき込まれ、プライドで肥え太ったマインドもスリムにシェイプアップされたのでした。
哲学の万能性
そんな中、私はある重大な事実に気づくことになります。
それは、最も難しい「セールス」という現場で結果を残してきたこの方法論は「人と世界の本質」に根ざしたものであり、人間を相手にする仕事であれば万能に機能するものであろうということ。
私なりのいくつかのカスタマイズはありましたが、私はこの方法論を「コーチング」という自分の仕事に全面的に取り入れることに成功しました。
というのも、当時、私は非常に大きな問題意識を感じ、壁に突き当たっていたのでした。
業界の限界
コーチングなど、人の内面にアプローチする人材開発において最も大きな問題は、いくらその人の心が動いても、その人の視点が低ければブレイクスルーは起きず、大きな結果は残せないということでした。
特に、複雑な状況に対応することが求められる企業文脈のコーチングや組織開発では、この問題はクリティカルなものとなってきます。
世の中、本当に結果を出す人は、すさまじいガッツと信念、大量の行動で視点を上げていくわけですが、必ずしもすべての人が、それをできるわけではありません。
「あなたは何がしたいの?」とコーチは問いますが、やりたいことが必ず実現できるわけではありません。
「答えはクライアントの中にある」とコーチングの先生は教えますが、クライアントがその答えを言葉で表現できるとは限りません。
そして、顧客が求めることは対象のクライアントが気持ちよくなることでは無く、その方が成長し、ビジネス上の結果を出すことです。
顧客からするとコーチングフィーは癒やしをもたらす福利厚生のための費用では無く、対象者が企業経営に貢献するための投資です。
コーチはクライアントの心と向き合いながら、こうしたスポンサーからの要請にも応えなければなりません。
クライアントとは別にお金を払うスポンサーがいる企業文脈でのコーチングは真面目にやろうとすると、結構、複雑な仕事です。
ブレイクスルーと信頼
当時の自分にとっては、まさにこの点が出口のない問題であり、仕事上の限界でもありました。自ずと、評価もそこそこに留まりますし、お仕事の単価も上がりません。
哲学が授けてくれる「メタ認知力」はこの点を一気に解決するものでした。
大事なことは構造を見通す目を磨くこと。
誰も悪気は無いけど、それぞれの一生懸命が絡まった毛糸の玉のようにからまり、どうしよう無くなっていくさま。これの絡まりきった構造を見切ることができれば、誰も悪者にせず、複雑な現状に着実な打ち手を打っていけるようになります。
そして、その構造を見る目は、クライアント自身の意識の変革、リーダーシップの質の向上にも大きく貢献するものでした。
このことを深く理解していけばいくほど、わたしは数々の難易度の高いプロジェクトで高い評価を得られるようになりました。
現在では格式ある経営者リーダー育成機関のプログラム統括コーチを担ったり、東証プライム上場企業の経営者育成プロセスに伴走するなどのステータスを得るに至っています。
おかげさまで、本当にありがたいことです。
とある経営者からは「マンガでもそんなストーリーはないぞ」と笑われたりもしますが、道なき道を切り開き、なんとか生きてこられた12年のプロセスでした。
運は良かったと思いますが、目の前に現れたチャンスを逃さなかったというのも、また、ここまで生き残れた要因でしょう。
上善如水
こうして培われた私の対話のスタイルは、独特の色合いを帯びており、ある人に言わせると「その人の人生やその人が関係する場の流れを良くするもの」となっているようです。
コーチングにおいては、その人の感情に深くアクセスすることでその人が覚醒し別世界へ突き抜けていくような関わりをされる方もいらっしゃいます。そうしたコーチングは派手で目立ちますが、私はそれとは少し趣が異なります。
私のスタイルは、複雑な状況の中で、深い現状認識と流れを良くする打ち手を通じて、単純な問題解決では無く「問題の解消」を狙う内省対話。
その人の内側と外側の両面の構造を見通し、その人が持つ先天的・後天的性質と、目の前に現れるテーマとの「連立方程式」の解を見いだし、必然の方向に流れを導いていく対話を得意としています。
「伏魔殿」といわれるほど複雑なステークホルダーが絡み合う霞ヶ関で長く過ごしたため直感的にわかるのですが、複雑な状況に直面し続けるエグゼクティブに対しては、おそらくその方が機能します。
理想は「上善、水のごとし」。
水はその器にしたがいながら、また、流れて盈(み)たず。
険を行きて、其(そ)の信を失わず。
水に関してはいろいろな諺がありますが、水はどんな険しい道であっても、その形を変えながら、必ずや海に出られるものと信じて止まらずに流れ続けます。
そんな、水のようにしなやかな、かつ、巌をも穿つような力強さを持ったマインドで道を切り開くお手伝いができればと思っています。
視点があがる歓びをお届けする
そして、同時に哲学塾塾長として、哲学を伝える側もつとめてきました(東京美学倶楽部哲学本部が主催する『哲学塾』は2025年4月を持って閉講。)。
かつて師がつくっていたようなビジネスや人生にダイレクトに使える哲学をはじめとするリベラルアーツを世の中の人にお届けするのことをライフパーパスとしています。
志としては、人生において、てつがくの「て」も思い浮かんだことのない人達に哲学の力をお届けしていくこと。
というのも、ビジネスは明確な目的のある世界です。
目的にフォーカスすることは大事ですが、目的だけにフォーカスしていては次第に視点が狭まっていきます。そして、この視野狭窄はその人だけに起こるわけではありません。会社や社会、そして文明自体もこの問題により行き詰まっていきます。
その問題への対処がリベラルアーツ教育の真髄。
今の自分では理解できないような抽象度の高い世界に触れて視点を高める実践は、ビジネスや人生の次元を変えるためにはとても有効な施策です。
視点があがると現実の戦闘力はあがります。
ただ、恩恵はそれだけでは無く、ちっぽけな自分の世界を脱皮し「本当の自分」に還っていくことで、より大きな富と幸せの流れに乗ることができる。
私はそちらの方が大事だと考えています。そして、その先には「視点があがること自体が歓びである」という感覚を得ることができるようになります。
自分の人生や取組の方向性に自分で「よし」といえるとき、その人の発する声は人々を感化するものとなり、その人の語る内容は人々に違う景色を見せるものとなっていくことでしょう。
そのような成長の道を、皆様とともに歩んでいければ幸いです。
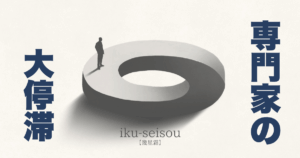
Organizer

Tony Yamada(山田 亨)
株式会社Flora Partners CEO。
エグゼクティブコーチ/経営者内省支援/リベラルアーツ教育家/Wines主宰。霞ヶ関の官僚を12年経験。
「視点が上がるという愛の実践」をモットーにカジュアルな知の伝道をライフワークとしています。
その他、民族系ゴスペル/唯識瑜伽行/美禅院享石など。


